社歌はあるか?の巻
町田の税理士 高橋浩之 です。

社歌、あなたの会社にありますか。会社の歌です。校歌みたいなものですね。
社歌ですか? もちろんありますよ。創業社長の作詞によるものでしてね。なかなか文才のあるかたでした。もうすこし貧乏だったら芥川賞のひとつやふたつとったんじゃないですかな。軍隊調でちょっと気恥ずかしいけど、いい歌詞です。朝礼で毎日合唱しています。もちろん、宴会の〆は、肩を組んでの大合唱ですよ。愛社精神がたぎりますなぁ。
このように、社歌にはなんとなく昭和の香りがします。ところが────、
そんな昭和の香り漂う社歌のコンテストが、令和の今、あるらしい。その名も「NIKKEI全国社歌コンテスト」。今年(2022年)で3回目だそうです。2月10日に決勝戦が行われました。
社歌の歌詞には当然、思いが込められるはずです。思いとはすなわち、会社の理念。会社の理念を伝えやすい形にしたのが社歌ともいえます。コンテストのサブタイトルは〝社歌は、鼓動だ。〟です。古臭いなどといわずに、会社の胸の響きを歌詞にして(社歌にして)世に問うみてはいかがでしょうか。もしかしたら、思いもよらぬ展開があるかもしれません。
いまの時期、店頭でよく見かける張り紙についての一考察、の巻
町田の税理士 高橋浩之 です。
■■■
毎年いまの時期にお店でよく見かける張り紙があります。いわく。「〇月〇日は、棚卸*1につき臨時休業させていただきます(あるいは、〇〇時までの時短営業とさせていただきます)」。小売業の会社は2月の決算が多い。よって、決算における大切な手続きである棚卸も、いまの時期に行われることが多いのです。
朝、りんごが1つ。昼に4つ買ってきて、夜寝る前にみてみたら2つ残っていました。夜、りんごの数を確認したのが棚卸です。そして、それによってわかるのは────減った数。

本来、減った数を知るのはたいへんです。四六時中りんごを見張っていなければならない。あなた以外のだれかが食べるかもしれませんから。見張りつつ、あなたやだれかが食べるたびにその数をメモしておく。面倒くさいし、時間もとられる*2。でも、こうでもしなければ、減った数はわからな・・・・・くない。そうだ。残っている数を数えればいいじゃないか。
減った数は、もともとあった数(1つ)に増えた数(買ってきた4つ)を足して、残っている数(夜の2つ)を引けばわかります。つまり、減った数(3つ)は、棚卸でわかる! 1日中見張っている必要はないんだ!

お店の棚卸もこれとおなじです。商品の減った数──お店の場合は売れた数*3──を追うのには限度がある。でも、棚卸をすればわかります。減った数がわかれば、減ったものの金額*4がわかる。減ったものの金額とは、すわなわち、売れたものの原価。原価がわかれば、利益が計算できます。つまり、お店が行う棚卸は、利益を計算するための大切な手続きだったのです。*5
*1:*棚卸
残っている商品(=在庫)を数える作業のこと。
*2:*面倒くさいし、時間も取られる
4つや5つのりんごならまだいいです。これが数百個のアメ玉だったら・・・時間をとられたうえに、もう何が何だかわからなくなる。
*3:*お店の場合は売れた数
理想は、減った数=(イコール)売れた数。でも、現実には商品が減るのは売れただけではありません。期限切れで廃棄した。あるいは万引き。こんな理由でも減ります。棚卸でわかるのはそのようなことも一緒くたにしての減った数です。売れた以外の理由で減った数は、別に管理しなければわかりません。
*4:*減ったものの金額
もともとあった在庫の金額(これはわかっている)+あたらしく仕入れた商品の金額(これも当然わかる)-在庫の金額(棚卸でわかった在庫の数×それを買ったときの値段)
*5:*棚卸は、利益を計算するための大切な手続き
棚卸には、それ以外の目的もあります。必要だけど持ち過ぎの在庫はないか。いらない在庫がないか。あるいは売れ筋商品の情報をつかむなど商品管理の意味でも大切です。
何もしていないのにできなくなって、何もしていないのにできるようになった件、の巻
町田の税理士 高橋浩之 です。
■■■
突然、電子メールが送信できなくなりました。さっきまでふつうに送れていたのに・・・・・。受信は正常。送るのだけがダメです。設定をいじった覚えはなく、それらしい原因は思い当たりません。
じつは、以前もおなじことがありました。そのときは、一晩寝たら直っていた(翌朝には正常になっていた)。
*アメリカの元統合参謀本部議長・元国務長官
まさに統合参謀本部議長にして湾岸戦争の英雄の言うとおりだったわけです。今回だってそうにちがいない。朝になれば状況はよくなっているはずだ。そう安心してぐっすり眠り、翌朝試してみるも────

送信はエラー。
一生懸命ネットで調べたところ、ある設定が原因らしいことまではわかりました。でも、それは間違っていない。ほかの正常に送信できるパソコンとおなじ設定です。なら、なぜ送信できないのか。設定をもう一度見直し、何度も見直し、パソコンを再起動してもダメ。こうなったら、業者に依頼するしかないな。こう思いつつも1日経ち、翌朝試しても送信できず。諦めかけていたその日の昼過ぎ────送信できました。設定は、送信できなかったときとおなじです。なぜでしょう?
いままでできていたことが突然できなくなり、あるときから突然できるようになった。その前後を通じて設定はおなじ。前回は一晩寝たら直って、今回は二晩かかった。これが顛末です。もし、またおなじことがあれば、つぎは三晩か。デジタルの世界はそういうふうにできているのでしょうか。・・・むずかしくてよくわからない。
統合参謀本部へ問い合わせてみようか。
医療費控除は10万円? の巻
町田の税理士 高橋浩之 です。
間もなく所得税の確定申告の時期がやってきます。2021年分(令和3年分)は、2022年2月16日から3月15日までがその期間です。
■■■
医療費控除は10万円?
「医療費控除は10万円」。よく耳にしますよね。年間の医療費が10万円ないと、医療控除は受けられない。もう少しで10万円超えたのに・・・・・。こんな嘆きの声を聞くこともしばしばあります。これを称して「医療費控除は10万円」というわけです(これから、医療費控除のために超えなければならないカベを「足切り額」と呼びましょう)。

じつは、足切り額は(収入が給与だけの人は)年収によって決まります。年収に基準があって、それに満たない年収の人の足切り額は10万円よりも少なくなるのです。その基準は、およそ300万円*1。つまり、年収が300万円に満たない人の超えなければならないカベは、10万円より少なくなる。みんながみんな「医療費控除は10万円」ではなかった!*2。
医療費控除は、いっしょに住んでいる家族から代表してだれかひとりが控除を受けることができます。ということは────家族の医療費全部で10万円なかった。せっせとせっせと領収書を集めてきたけれど、医療費控除はあきらめるしかないな・・・ではなく、だれか年収300万円未満の人がいないか確認しましょう。いれば、その人の足切り額と医療費を比較。足切り額を超えていたら医療費控除が受けられます*3。
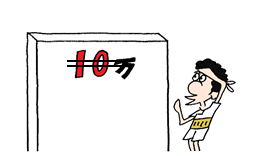
医療費控除、あきらめるその前に。ぜひご検討を。
オフィスには、目標とすべき湿度がある!の巻
町田の税理士 高橋浩之 です。
■■■
オフィスには、目標とすべき湿度がある
「40%以上70%以下になるよう努めなければならない。」労働安全衛生法にもとづく事務所衛生基準規則では、オフィスの湿度についてこう定めています。湿度についての法令があるなんて・・・すこしおどろきですね。
いまの時期はとくに湿度が下がります。やっかいなウイルスの感染力を下げるためにも、加湿は大切。我が事務所でも空気清浄機を置いて、加湿にこれ努めています。
じつは、この清浄機がよくしゃべるんです。曰く、空気の汚れをみつけた。曰く、空気がきれいになった。曰く、空気が乾燥しているから急いで加湿する、などなど。挙句の果てには、言うことがなくなると「う~ん、いい気持ち!」(←ほんとうにこう言う)と現在の心境を述べたりします。だまらせる設定もできるのだろうけど、まあ、いまは言いたいがまま言わせている状態です。
と、ここまで書いて空気清浄機に目をやると────なんと、表示されている湿度は22%! 基準を大きく下回っている! ややや、事務所衛生基準規則に反しているじゃないか。こう思いきや、そうではありません。求められているのは「40%以上70%以下の湿度」ではなく「(その範囲の湿度になるよう)努めること」です。タンクの水がなくなれば補充しているわけで、これを努めていると言わずになんと言おう。ゆえに法令違反はないということで。
もちろん、これからも、努めます!
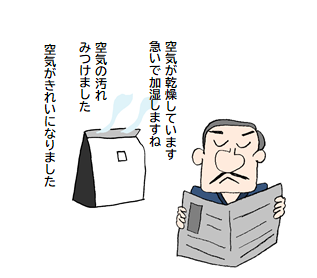
丑から寅へ、の巻
町田の税理士 高橋浩之 です。
■■■
丑から寅へ
あたらしい年になりました。遅ればせながら今回が2022年最初の投稿です。
昨年(2021年)の干支を覚えていますか? ・・・・・すぐには出てきませんかね。丑が正解です。干支なんて、年賀状の図柄を考えるときしか気にしませんからそれも当然。
牛には、ゆっくり、のんびりといったイメージがあります。とはいえ、現代は万事が迅速、スピード重視の時代です。急げや急げ、やれ急げ。のんびりしていたら、取り残されるぞ。牛のようには生きにくい世の中かもしれませんね。そんな牛から連想される言葉があります。バングラデシュに伝わるものです。1年間お世話になった(?)牛に感謝を込めて、それを紹介しましょう。
さて、今年は寅年です。
「虎を描いて猫に類す」。こんな成句があります。あまり、なじみはないですよね。意味は────勇猛な虎を描こうとして、猫のようになってしまう。転じて、力量のない者がすぐれた人のまねをして、かえって軽薄になることのたとえ。また、目標が大きすぎて失敗することのたとえ。
ほんとうは、「猫に類す」ではなく、「狗(いぬ)に類す」だといいます。まあ、それはともかく、要は、身の丈に合ったことをしましょうという戒めです。

特別なことをしなくてもいい。自分の身の丈に合ったことをただ続けるだけ。もしかしたら、それが並外れた結果にむすびつくかもしれません。
ウォーレン・バフェット(アメリカの著名な投資家。別名「オマハの賢人」)

ことしもお世話になりました、の巻

ことしもお世話になりました。来年もよろしくお願いいたします。
■ 1年お世話になった(?)牛にから連想される言葉を紹介。
ゆっくり歩いて休まない。そんな人にはだれも敵(かな)わない───バングラデシュのことわざ

